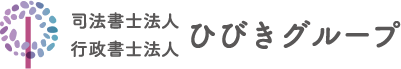2/15・2/16緑区・天白区の相続・家族信託の土日相談会
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2025/2/10
- 2025/2/10
緑区・天白区の相続対策・相続手続き・家族信託の土日相談会開催!
相続や家族信託のご相談について、土日の無料相談会を実施いたします。
場所は、司法書士法人ひびきグループ(緑オフィス)となります。
名古屋市緑区・天白区・東郷町・豊明市・日進市の方は、大変便利な場所ですので、ぜひご利用ください。

おひとりで悩まれずに。2/15・2/16の相談会でお待ちしております。
| 日時 | 2月15日(土)・2月16日(日) |
| 場所 | 司法書士法人ひびきグループ 緑オフィス (名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地) |
| 相談費用 | 無料 |
| 相談内容 | 相続に関すること(相続対策・相続手続きなど)、家族信託に関すること(認知症対策など) |
| 相談予約 | 事前に相談予約をお願いします |
相続・家族信託について、土日に相談したい、話を聞いてみたいという方は、是非ご利用ください。
- 相続の対策について、土日休みで相談に行きたい
- 平日は仕事があるので、土日に家族信託の話を聞いてみたい
- 相続で不動産の名義変更ができずそのままになっているので、手続きについて聞きたい
- 親の認知症で財産凍結が心配。家族信託の内容について知りたい
- 相続した不動産の売却を考えており、手続きや不動産会社を紹介してほしい
など、相続と家族信託のことなら、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
ご相談は、
 相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。
緑区で相続の相談なら緑オフィスへ、お気軽にご相談ください。相続の不安を、一緒に解決していきましょう。
※名古屋駅オフィスでのご相談をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
緑区の相続相談ひびきグループへのアクセス
住所:名古屋市緑区亀が洞1-707
駐車場は、以下の駐車場をご利用ください。

相続に関する情報のご案内
2/3(月)のYahoo!ニュースで司法書士 西風恒一先生による『相続登記にかかる期間は? 必要な準備から日数短縮のコツ、司法書士に依頼するメリットまで解説』という記事がありましたのでご紹介します。
不動産の登記名義人が亡くなった際には、法務局に申請して相続人の名義に変更します。これを「相続登記」と言い、2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。ただし、相続登記の手続きでは準備から完了までにどのくらいの期間を要するのかわかりづらいと思います。相続登記にかかる期間や日数短縮のコツを司法書士が解説します。
1. 相続登記の手続きにかかる期間はどのくらい?
1-1. 被相続人の所有不動産調査にかかる期間
まずは被相続人(以下、亡くなった人)が所有していた不動産を漏れなく調査する必要があります。自宅などに保管されている権利証を確認するほか、市区町村役場から毎年送付される固定資産納税通知書を見れば、おおよその所有不動産を把握できます。
しかし、不動産には、たとえば自宅周辺の公衆用道路のように、課税されないものがあります。こうした非課税の不動産を所有している場合は固定資産納税通知書には記載されていないため、同通知書だけでは把握できず、見落とすケースがあります。
漏れなく把握するためには、固定資産納税通知書の確認と併せて「名寄帳(なよせちょう)」を請求する方法があります。名寄帳とは、市区町村が作成している固定資産税台帳を所有者別にまとめたものです。ある人の所有不動産を知りたい場合に、市区町村ごとに請求することで、その人がその市区町村に所有する不動産を一覧にして発行してもらえます。
亡くなった人の名寄帳を請求する場合は、名義人と請求者の相続関係を証明する戸籍謄本などの提示が必要です。
所有不動産を漏れなく調査するには、おおよそ1週間〜2週間かかる場合があります。なお、2026年(令和8年)2月2日より、法務局で全国に所有する不動産を一覧で証明してもらえる「所有不動産記録証明制度(仮称)」がスタートする予定です。この制度を利用することで、不動産の調査にかかる期間の短縮が期待できます。
1-2. 相続人調査にかかる期間
法務局に相続登記を申請する際には、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本、そして各相続人の現在の戸籍謄本を提出する必要があります。相続人となるべき人を確定し、相続手続きが適切に行われていることを証明するためです。
戸籍謄本などの収集にかかる期間は相続関係によってさまざまですが、相続人が配偶者と子どものみである場合は、郵送で取り寄せても2週間〜3週間で完了するケースが大半です。
しかし、子どもがおらず両親も亡くなっており、兄弟姉妹が相続人になるケースや、相続人であった人物がさらに亡くなっているケースでは、1カ月〜2カ月かかることもあります。
なお、令和6年3月1日より戸籍の広域交付制度がスタートしました。ほかの市区町村役場の戸籍謄本であっても、最寄りの市区町村役場で一括して取得できる制度です。この制度を利用することで相続人調査の期間を大幅に短縮できます。
1-3. 遺言書の検認が必要な場合にかかる期間
遺言書が作成されており、それにもとづいて相続登記をする場合は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本のすべてを準備する必要はなく、亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本と、遺言により不動産を取得する人が遺言者の相続人であることを証明できる戸籍謄本のみをそろえることで足ります。
公正証書遺言、または法務局保管制度を利用した自筆証書遺言がある場合は、特別な手続きを経由せずに相続登記ができます。一方、法務局以外の場所で保管されていた通常の自筆証書遺言については、家庭裁判所での「検認手続き」を経なければ相続登記に使うことができません。
検認手続きは、遺言書の適格性や効力を審査するものではなく、遺言書の内容を確認し、偽造や変造を防止する目的で行われるものです。手順としては、必要書類を準備し、遺言者、つまり亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。そのあと各相続人に検認期日についての通知が送られ、指定された日に相続人が家庭裁判所に出席して検認手続きが行われます。
検認手続きを済ませたら、家庭裁判所から検認済証明書を発行してもらいます。自筆証書遺言に検認済証明書を添付し、その他の必要書類と一緒に法務局へ提出することで相続登記の申請ができます。
検認手続きの申立てから検認終了までは、数週間~1カ月程度かかると考えておくとよいでしょう。また、申立ての準備には遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等及び相続人の戸籍謄本をそろえる必要がありますので、そのぶんの期間も必要です。
1-4. 遺産分割の話し合いにかかる期間
遺言書がなく、法定相続分どおりに相続登記をしない場合は、遺産の分け方について話し合う遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」を作成します。これに相続人全員が署名または記名し、捺印または実印での押印をしなければ相続登記に使用できません。
遺産分割協議がすぐにまとまり、相続人全員からの記名押印または署名押印がスムーズにいけば、一般的に1週間〜2週間で遺産分割協議書が完成します。一方で、遺産分割協議が難航するケースや、相続人が遠方に住んでいて郵送でのやり取りが必要になるケースでは、遺産分割協議書作成までに数カ月、長ければ数年かかる場合もあります。
せっかく遺産分割協議が整っても、遺産分割協議書に不備があると署名捺印のやり直しになりかねないため、司法書士に依頼するのが確実でしょう。
1-5. 相続登記申請書の作成にかかる期間
必要な書類がそろったら、登記申請書を作成します。法務局の公式サイトなどを参考にしたり、法務局の登記相談でアドバイスを受けたりしながら、申請書を作成できます。
作成にかかる期間は一律にどの程度というものではなく、1日で完成する場合もあれば、1週間かかる場合もあります。申請後に不備があれば、原則として法務局に出向いて補正を行うことになります。法務局が遠方にある場合はかなりの負担になるため、不安がある場合は司法書士に相談しながらの進行も検討しましょう。
遺産分割協議をした場合における相続登記の一般的な必要書類は以下のとおりです。
・登記申請書
・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・亡くなった人の登記記録上の住所と最後の住所のつながりを証明する書類(住民票除票または戸籍の附票)
・不動産を取得する相続人の住民票、または戸籍の附票
・固定資産納税通知書、または不動産評価証明書(コピー可)
1-6. 申請から登記完了までにかかる期間
法務局に登記申請をしてから登記が完了するまでは、平均すると1週間〜10日程度かかりますが、そのときに法務局が抱えている申請件数によっても変わります。完了予定日は法務局の窓口やインターネットで確認することができます。
登記が完了すると、登記識別情報通知および登記完了証が交付されます。登記完了後の登記事項証明書や登記簿謄本は、別途法務局に請求して発行してもらいます。窓口請求の場合、交付手数料は1通あたり600円です。
なお、登記識別情報通知は権利証に代わるものです。2005年の不動産登記法改正によって権利証は廃止され、登録識別情報通知が発行されることになりました。
2. 相続登記の手続きが長引いてしまうケース
相続登記の手続きが長引くのは、主に以下の4つのケースです。
2-1. 遺産分割協議がまとまらない
遺言書がなく、遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分どおりに登記する以外に相続登記をする方法はありません。
遺産分割について相続人の間に争いがある場合などは、話し合いがまとまるまでは遺産分割協議書が作成できず、相続登記をすることができません。
このような場合は、まずは弁護士に依頼して遺産分割をまとめるところから始めます。場合によっては家庭裁判所に申立てをして遺産分割調停を行う必要があります。
2-2. 連絡がとれない、とりにくい相続人がいる
相続関係が複雑で、会ったこともない関係者が相続人に含まれているケースがあります。このような場合は、まず手紙を送るなどして手続きの協力を求めることになりますが、必ずしも連絡がとれるわけではなく、話し合いができるまでに時間がかかる場合もあります。
また、相続人のなかに行方不明の人がいる場合は、不在者財産管理人の選任申立てを裁判所に行う必要性が生じる可能性もあります。
2-3. 先祖代々登記がされていない
自分の親名義の不動産について相続登記をする場合は、相続人同士の関係が良好であればさほど手続きに時間はかかりません。しかし、たとえば長期間放置されていた祖父名義の不動産について相続登記をしようとすると、戸籍謄本などの収集だけでも相当の時間がかかります。
その理由は、登記名義人の子ども世代にも相続が発生しており、子の相続人、つまり登記名義人の孫世代の調査が必要になるケースが多いためです。また、そうなるときわめて関係性の薄い人同士が相続人となるため、話し合いにたどり着くまでにかなりの時間を要します。
2-4. 相続人や相続不動産が多い
相続人が多い場合は書類の収集や連絡事項の伝達に時間がかかるため、全体的に手続きがスムーズに進みにくい状態となります。
また、法務局の管轄が異なる複数の不動産の相続登記をする必要がある場合は、一般的には一つの管轄の登記が完了したあと、順に返却された書類を次の管轄の申請に添付することになります。そのため、相続登記の対象となる不動産がいくつもの管轄にまたがる場合は、そのぶん時間がかかります。
3. 相続登記の手続きにかかる日数を短縮するコツ
相続登記をするにはある程度の時間がかかります。手続きを少しでもスムーズに進めるためには、特に以下の3点に留意しましょう。
・遺産分割の話し合いを少しずつ進めておく
・相続人で協力し合って書類を集める
・司法書士に相談や依頼をする
3-1. 遺産分割の話し合いを少しずつ進めておく
遺産分割協議は、亡くなった人の遺産を相続人がどのように分けるかという話し合いであるため、遺産の全貌が明らかになっていないと話し合いができません。できるだけ早めに相続財産を調査し、話し合いを少しずつ進めておく必要があります。
3-2. 相続人で協力し合って書類を集める
相続人同士での話し合いがまとまっている一方、戸籍謄本などの書類を集めるのに時間がかかる場合は、協力が得られるのであれば各相続人が手分けして準備するとよいでしょう。また、戸籍の広域交付制度を利用すれば、直系の親族の戸籍謄本は最寄りの役所だけで取得できるため、この制度も活用してください。
3-3. 司法書士に相談や依頼をする
司法書士には戸籍謄本などの職務上請求が法律で認められており、、相続人同士の話し合いを除くすべての手続きを任せられます。日常業務として相続登記を行っている司法書士に依頼をすれば、全体的なスピードは自分で行うよりもかなり早くなるはずです。
4. 相続登記の手続きの期限は?
相続登記の義務化により、相続登記には「不動産の所有権を相続したことを知った日から3年」という期限が設けられました。また、期限内に相続登記をしなければペナルティーが科せられることになりました。
4-1. 3年以内に登記申請しなければ10万円以下の罰金
相続登記義務化に関する規定のなかで、相続登記の期限について以下のように定められています。
・相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
・遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならない
これらの規定に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となります。
相続登記がすぐにできない場合の対応策として、自分が相続人であることを申告し、ひとまずその旨を登記しておくことでペナルティーの対象から外れる「相続人申告登記」の制度も用意されています。
4-2. 2024年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象
相続登記の義務化がスタートしたのは2024年4月1日ですが、それ以前に亡くなった人の名義である不動産も義務化の対象となります。その場合は、「2024年4月1日」「不動産を相続したことを知った日」のいずれか遅いほうが起算点となり、その日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
5. まとめ|相続登記の日数を短縮したい場合は司法書士に依頼を
相続登記の手続きは、複雑ではないケースでは自分で準備して申請しても、さほど時間をかけずに済ませることができます。しかし、申請に必要な書類は数多くありますし、慣れていないためいろいろ調べたり、問い合わせに時間を要したりしてなかなか進まないケースもあります。
また、内容や相続人の関係性などが複雑な場合には、相続登記の申請をする以前にさまざまな調査や手続きが必要になるため、さらに多くの時間と労力を要することになります。相続登記にかかるストレスを軽減するには、司法書士に依頼するのがお勧めです。
司法書士はさまざまなケースに対応している相続登記の専門家であり、複雑なケースでもスムーズに進めてもらえます。相続登記の手続きに不安があれば、司法書士への相談を検討してみてください。
相続に関する各種手続きは弁護士が対応できるものが多くありますが、不動産の名義変更手続きは司法書士が行うのが一般的です(トラブル対応の一環として弁護士が対応する場合もあります)。
相続人同士などでトラブルが起きていない限りは司法書士、と覚えておいたほうがわかりやすいでしょう。
当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。
相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。

相続対策のご相談
自分の親や自分自身の将来の相続に向けて、終活を考えていきたい、相続税について知っておきたい、子どもたちがもめないように財産分与の遺言書や生前贈与を検討したいという方は、相続対策についてご相談ください。
認知症対策としての家族信託のご相談も多くいただいています。
後にのこされるご家族のために、元気なうちに、必要な対策を取っておくことが重要です。
相続税の無料試算と節税対策
相続税の対策については、相続税に強い税理士をご紹介させていただき、相続税の試算から対策を行います。
相続税の節税対策は、早くやればやるほど効果が出ます。
まずは、相続税の簡易試算を行い、有効と考えられる相続税対策(暦年贈与対策や生命保険の活用など)を提示します。
その上で、現状のままだと相続税がいくらになるか、それぞれの対策を行うと税金がいくらになるかをシミュレーションして、実際に行う手続きを一緒に考えていきます。
認知症の対策(家族信託)
近年は、認知症の問題が大きな社会問題となっており、認知症対策として家族信託や任意後見を考えられる方が非常に多くなっています。
特に、最近注目されている家族信託は、NHKの番組でも特集が組まれるなど、認知症への備え・家族の中での財産管理として、多くのご相談をいただいています。
詳細は、名古屋の家族信託相談所のページをご覧ください。
家族信託のご相談は、お子さんが親の認知症を心配されて来られるケースも多く、ご本人がいなくてもご相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。
当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。
相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。


相続の対策・生前対策に関するご相談は、司法書士法人ひびきグループでも多くご相談いただく内容です。
特に、緑区や日進・豊明にお住まいの方は、土地をお持ちで相続財産の割合の多くを不動産が占めている方(金融資産の割合のほうが少ない方)など、遺産分割で支障が出る可能性がある方も多くいらっしゃいます。
先々の財産の承継を考え、財産分与の方法や、遺言書や生前贈与、生命保険での財産承継など、元気なうちにいろいろなことを準備しておくことが大事です。
終活を考える
また、最近は終活にも注目が集まっており、財産のことだけではなく、家系図を作成したり、エンディングノートを作成したり、葬儀のことを考えたり、さまざまなご相談があります。
終活のことも含め、相続に関することは、まずは一度ご相談いただければと思います。
相続手続きのご相談
実際に相続が起こった後の手続きとしては、亡くなった方の出生から死亡まで(生まれてから亡くなるまで)の戸籍謄本の取得や、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、不動産の名義変更(相続登記)、生命保険金の請求など、多くの手続きが必要となります。
遺産分割協議では先々のリスクを検討して相続することが必要
遺産分割では、相続人のうち誰が承継をするのか、特に不動産はこの先引き継いで将来的に売却する可能性があるとしたら誰が相続するとよいのかなど、手続きや税金面も含め、色々な角度からの検討が必要となります。 司法書士のほか、相続につよい税理士とも連携して、お客様の相続に関するサポートが可能です。
家族信託のご相談(認知症対策)
家族信託は、高齢化社会の中で、認知症による財産凍結の問題が大きくクローズアップされており、NHKや新聞などでも取り上げられ、特に近年ご相談が急増している内容です。
認知症で意思判断能力が低下すると、預貯金がおろせなくなったり、自宅の不動産を売却しようと思っても売れなくなってしまう(売買契約自体ができなくなる)という状況になってしまいます。
家族信託とは?家族信託の仕組み
家族信託では、信頼できる家族に財産を預け託し、財産の管理を任せるという仕組みをつくることができます。 ご本人の意思がはっきりしていて元気なうちに、財産をどうやって活用しくかを話し合い、それに沿って、将来の備えを行います。
家族信託の注意事項
※家族信託は、委託者(財産を預ける人)について、家族信託を行うことの意思能力が必要となります。
認知症で家族信託の契約を締結するという意思判断能力がなくなった後では行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
認知症の程度など、詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
相続相談や認知症の不安・家族信託のご相談はひびきグループへ
相続のご相談、家族信託のご相談は、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
担当の司法書士、行政書士、相続信託コンサルタントが、親身に相談に対応させていただきます。
ご相談の際は、担当者が出張相談等で外出している場合がありますので、事前にご予約をお願いいたします。
ご相談は、 相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
相談予約 ☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。
また、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。 ご相談お待ちしております。