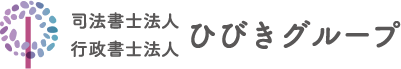相続放棄
- 2015/3/15
- 2021/12/17
遺産相続は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も承継してしまいます。 マイナスの財産は相続したくないということであれば、相続放棄の手続きをする必要があります。 相続放棄とは、被相続人の一切の財産を承継せず、放棄するという手続きです。 相続放棄をすると、「最初から相続人ではなかったもの」という扱いになります。 そのため、プラスの財産はほしいけど、マイナスの財産だけ放棄する ということはできません。 相続放棄をした場合は、被相続人名義の預貯金や不動産などについても、一切相続しません。 なお、借金がある場合だけでなく、
- 被相続人とは、生前にケンカをしていて、顔も見たくない。何かを相続するつもりもないので、一切かかわりたくない。
- 遠い親戚で、ほとんど関わりがなかったので、遺産分割協議にも参加したくない。後は親戚の方で手続きを進めてほしい。 というような場合に、相続放棄をされるケースも多くあります。
相続放棄の手続き
相続放棄は、
①被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、
②家庭裁判所に対して、相続放棄の申し立てをする
という手続きが必要です。
申し立ては、亡くなった被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所に申し立てます。
相続放棄の必要書類
共通で必要になる書類
- 被相続人の住民票除票or戸籍附票
- 申立人の戸籍謄本
配偶者が申立てをする場合
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
子・孫が申立てをする場合
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 孫が申立てをする場合,子(孫から見て親)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
父母が申立てをする場合
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子が死亡している場合,その子の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 祖母が申立てをする場合、父母(祖母から見て子)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
兄弟姉妹が申立てをする場合
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子が死亡している場合,その子の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- おい・めいが申立てをする場合,兄弟姉妹(おい・めいから見て親)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
相続放棄の注意点
一番注意すべきことは、
「亡くなったことを知ってから3ヶ月以内」に 手続きをしなければならないという点です。
3ヶ月経過すると、相続を承認したことになります(単純承認)。
なお、もし3ヶ月経過してしまった場合でも、相続放棄ができる場合もありますので、 その場合はお早めにご相談ください。 (3か月経過後の相続放棄参照)
3カ月以内に間に合わない場合
相続放棄の申立てが、熟慮期間である3カ月以内にできないときは、相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てをすることができます。 いずれにしても、早い段階で被相続人の財産を調査することが先決です。
相続放棄と遺産分割の違い
よく間違われるのは、
「遺産分割で何も相続しないことにしたから、借金も相続してない」
ということです。
これは、大きな間違いです。
遺産分割で相続しないと決めたとしても、
債権者(貸金業者)に主張することはできません。
借金を相続しないためには、「相続放棄」をするしかありません。
借金がある場合は、安易にハンコを押さないようにしましょう。 詳細は、相続放棄と遺産分割協議の違いをご覧ください。
相続放棄の手続費用
| 手続き内容 | 司法書士費用(報酬) |
| 相続放棄 | 68,000円 |
| 必要書類取得(戸籍謄本・登記簿謄本等) | 1通につき800円 |
その他、相続放棄の料金詳細は、相続放棄の料金プランをご覧ください。
※同時に2名以上の方の相続放棄手続きを行う場合は、費用を割引させていただきますので、お気軽にご相談ください。
※案件や内容により、追加費用が必要となる場合がございます(事前にご説明いたします)。
※手続きに必要な戸籍取得等の実費(切手・小為替)や、法務局・裁判所への申請実費(収入印紙・登録免許税)等は別途必要になります。
※上記は税抜き価格です。消費税分は別途ご精算いたします。